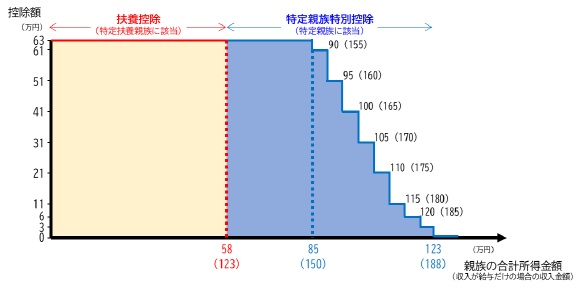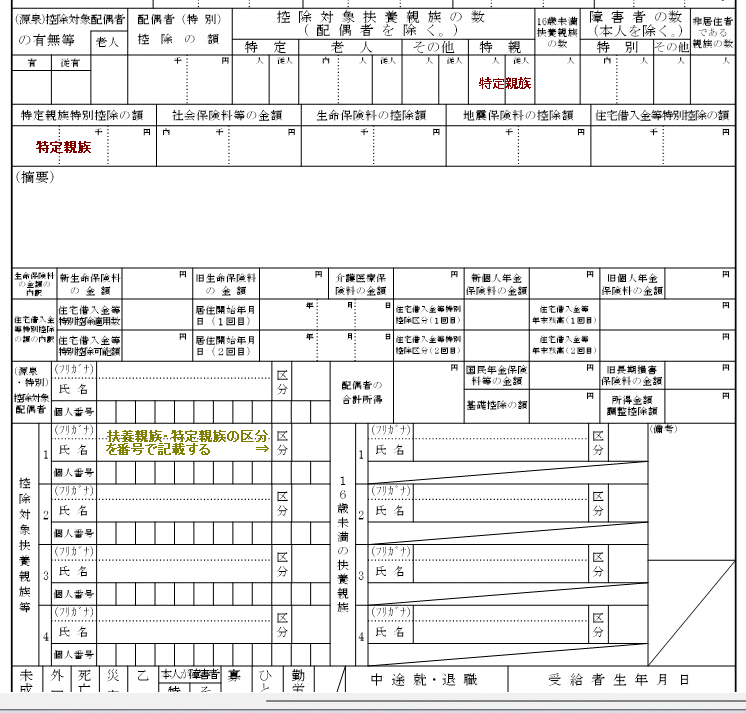|
【令和7年
年末調整】
1.基礎控除
合計所得金額に応じて0円~95万円になりました。
|
合計所得金額 |
令和6年まで |
令和7・8年 |
令和9年以降 |
|
132万円以下 |
48万円 |
95万円 |
58万円
|
|
132万円超
336万円以下 |
88万円 |
|
336万円超
489万円以下 |
68万円 |
|
489万円超
655万円以下 |
63万円 |
|
655万円超 2,350万円以下 |
58万円 |
|
2,350万円超 2,400万円以下 |
48万円 |
48万円
|
|
2,400万円超 2,450万円以下 |
32万円 |
|
2,450万円超 2,500万円以下 |
16万円 |
|
2,500万円超 |
0円 |
令和9年以降の基礎控除額は令和7年現在の規定です。
2.給与所得控除
給与の収入金額が190万円以下の場合の給与所得控除額が引き上げられました。190万円超の場合の給与所得控除額は改正前と同額です。
|
給与の収入金額(A) |
給 与 所 得 控 除 額
|
|
円超 |
円以下
|
令和6年まで |
令和7年以降 |
|
|
1,625,000
|
55万円 |
65万円
|
|
1,625,000
|
1,800,000
|
A×40%-10万円 |
|
1,800,000 |
1,900,000
|
A×30%+8万円 |
|
1,900,000
|
3,600,000 |
A×30%+8万円 |
|
3,600,000
|
6,600,000
|
A×20%+44万円 |
|
6,600,000 |
8,500,000
|
A×10%+110万円 |
|
8,500,000
|
|
195万円 |
3.扶養親族等の要件
上記1及び2の改正により、扶養親族等の所得要件が改正されています。
|
扶養親族等の区分 |
所得要件(
括弧内は収入が給与所得だけの場合 ) |
|
令和6年まで |
令和7年以降 |
|
扶養親族 |
48万円(103万円)以下 |
58万円(123万円)以下 |
|
配偶者特別控除の対象者となる配偶者 |
48万円(103万円)超
~ 133万円(202万円未満) |
58万円(123万円)超
~ 133万円(202万円未満) |
|
勤労学生 |
75万円(130万円)以下 |
85万円(150万円)以下 |
控除対象扶養親族については、次の区分番号を源泉徴収票(給与支払報告書)の「控除対象扶養親族等」の「区分」欄に記載します。
|
控除対象扶養親族の分類 |
区 分 |
備 考
|
|
居住者 |
00※1 |
※1 源泉徴収票を書面で税務署へ提出する場合は、空欄とする
|
|
非居住者(30歳未満又は70歳以上) |
01 |
|
|
非居住者(30歳以上又は70歳未満、留学生) |
02 |
留学により国内に住所及び居所を有しなくなった扶養親族人
|
|
非居住者(30歳以上又は70歳未満、障害者) |
03 |
|
|
非居住者(30歳以上又は70歳未満、38万円以上送金)
|
04
|
生活費・教育費として年間38万円以上受けている扶養親族
|
国税庁の「作成の手引き」には「非居住者である場合には、次の分類に応じて次のように記載してください」と記されていますので、居住者については区分番号は記載不要のはずですが、居住者=「00」が設定してあり、※1の注意書きからは「税務署提出用以外」には、居住者=「00」を区分欄に記載すると読めます。果たして記載する・しない?
それとも任意?(記載しても問題はないようです)。
4.特定親族特別控除(創設)
特定扶養親族(年齢19歳以上23歳未満)に対しては63万円の所得控除の適用がありますが、該当親族の所得金額が58万円(改正前は48万円)を超えると適用外になり、以前から「働き控え」の一因との指摘がありました。緩和策として、該当親族の所得金額が
58万円~123万円(給与所得だけの場合は123万円~188万円)であれば一定額の控除が受けられるように、特定親族特別控除が創設されました(配偶者控除と配偶者特別控除の関係に類似した制度です)。
表の区分(10~91)を、源泉徴収票(給与支払報告書)の「控除対象扶養親族等」の「区分」欄に記載します。
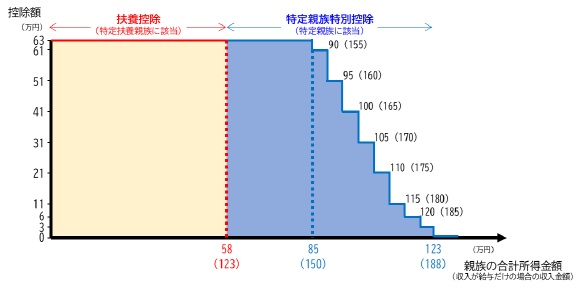 |
特定親族の合計所得金額
|
特
定 親 族
特別控除額
|
区 分
(特定親族
が居住者) |
区 分
(特定親族が
非居住者) |
|
万円超
|
万円以下
|
|
58(123)
|
85(150)
|
63万円
|
10 |
11 |
|
85(150)
|
90(155)
|
61
|
20 |
21 |
|
90(155)
|
95(160)
|
51
|
30 |
31 |
|
95(160)
|
100(165)
|
41
|
40 |
41 |
|
100(165)
|
105(170)
|
31
|
50 |
51 |
|
105(170)
|
110(175)
|
21
|
60 |
61 |
|
110(175)
|
115(180)
|
11
|
70 |
71 |
|
115(180)
|
120(185)
|
6
|
80 |
81 |
|
120(185)
|
123(188)
|
3
|
90 |
91 |
( )の金額は給与所得だけの場合です。
5.源泉徴収票(給与支払報告書)
特定親族欄が追加され、「控除対象扶養親族」が「控除対象扶養親族等」に変更されています。
なお、個人住民税の基礎控除額・所得割の基本額は据え置きになっていますので、単身者の場合で給与収入だけの場合の(所得割の)非課税額は
110万円(65万+45万)になります (総務省)。
【令和6年
年末調整】
定額減税に関する項目が増えました。
◆
定額減税の対象者
|
本人 |
合計所得金額が
1,805万円 以下 |
所得税の控除額は各3万円(住民税は各1万円)
|
|
配偶者 |
合計所得金額が
48万円 以下 |
|
扶養親族 |
合計所得金額が
48万円 以下の扶養親族で、扶養控除の対象でない年少扶養親族を含みます |
所得税の控除額は対象者数
× 3万円( 〃 )
|
◆
年税額の計算
|
差引課税給与所得金額及び算出所得税額 |
4,990,000 |
570,500 |
|
|
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額 |
|
|
|
年調所得税額 |
570,500 |
年間の所得税額 |
|
年調減税額 |
90,000 |
定額減税の合計額 |
|
年調減税額控除後の年調所得税額 |
480,500 |
マイナスの場合は「0」 |
|
控除外額 |
|
マイナスの場合の金額 |
|
年調年税額
( 年調減税額控除後の年調所得税額×102.1%
) |
490,500 |
復興特別所得税を含む金額(100円未満切り捨て) |
|
差引超過額又は不足額 |
|
|
◆
源泉徴収票・給与支払明細書 …
年末調整で控除した定額減税額及び控除仕切れなかった額=控除外額を、摘要欄に記載します。
その他、令和5年からの改正はありません。
【令和3年~5年
年末調整】
年末調整に際して従業員が勤務先に提出する各申告書(給与所得者の扶養控除等申告書、給与所得者の配偶者控除等申告書、給与所得者の基礎控除申告書、給与所得者の保険料控除申告書など)を電子データで作成・提出するには、従来税務署長の承認が必要でしたが、令和3年分から承認は不要になりました。
また、PC又はスマホで各申告書を作成するソフト(アプリ)を国税庁が公開しています。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nenmatsu/nencho.htm#soft_dl
その他、令和2年からの改正はありません。
|